禁止って書いてるけど、もしタンブラー乾燥したらどうなるの?
タンブラー乾燥禁止なのはわかった。でも普通に乾かせば時間がかかるしどうやって乾かせばいいの?
この記事ではこんな疑問にお答えします。
睡眠環境・寝具指導士で現役の寝具業界の営業マンのしーさんが解説します。
最近では洗えるお布団も増えてきてお布団を家庭洗濯する機会が増えてきています。
ただその時に気になるのが乾燥方法ですよね。
お布団は基本的にタンブラー乾燥禁止の洗濯絵表示がついています。
お布団は天気のいい日に干しても乾くまでに時間がかかってしまったり、羽毛布団や羊毛布団の場合は半乾きだと臭いが気になったり、元通りにふっくらしなかったりと洗うことより乾かすことが難しいです。
先に結論を書いておくと、タンブラー乾燥はやめてください。
この記事ではタンブラー乾燥すると何故ダメかという点と解決方法について解説していきます。
- お布団をタンブラー乾燥するとダメな理由
- タンブラー乾燥できなければどうすればいいか

お布団をタンブラー乾燥すると何故ダメなのか?

確認しておくべき洗濯絵表示
通常洗うことができない羽毛布団などには画像のような洗濯絵表示がついているかと思います。
これはお布団についている品質表示のタグのところ記載があります。
まず、この洗濯絵表示が記載されているお布団はメーカー側が洗濯を禁止しているお布団になるので、洗って何かトラブルが起こった場合、保証の対象外になります。
勝手に洗うのは個人の自由だけど、メーカーとしては保証しませんよーということですね。
それでは何故お布団をタンブラー乾燥するとダメなのか?
どんなデメリットやリスクがあるのか。
3つにわけて解説していきます。
生地が傷んだり型くずれする
お布団をタンブラー乾燥すると生地が傷んだり、型くずれします。
お布団は大きいので普通の乾燥機では基本的にスペースをいっぱい使うことになります。
そうなってしまうとタンブラーのなかでお布団が動かなくなってしまい、同じ場所に熱が当たり続けることになってしまうんですよね。
このような状態が長く続けば生地が焦げたりする可能性がありますし、焦げた部分が劣化して穴があく可能性があります。
穴が開いてしまうと中綿の吹き出しにも繋がりますし、最悪の場合ですが中綿が燃える可能性もあるかもしれません。
中綿が燃えるというのは誇大表現かもしれませんし、僕が知っている範囲ではそのような事例はありませんが、焦げたという事例は聞いたことがあります。
焦げたという事例が起きてからタンブラー乾燥禁止が安全性の面も考えて一般化されていったようです。
お布団やカバーが縮む
生地にポリエステルが多く使われている場合は綿100%のものと比較してもまだマシですが、それでも縮みます。
これは乾燥というよりは水洗いした場合のデメリットでもあるのですが、基本的にお布団やカバーは洗うと縮みます。
デニムなんかでも洗ったあとは一回り小さくなった気がしませんか?
多分みなさん一度は衣類が縮んだ経験があるかと思いますが、お布団も一緒なんですよ。
洗えるお布団やカバーの場合は防縮加工や元々縮みにくい素材を使っていたりするので、そこまで大きく縮むことはないのですが、元々洗えないお布団を無理矢理洗うと7%~10%程度縮んでしまうこともあります。
シングルサイズのお布団の場合、150㎝×210㎝なので仮に10%縮むと135㎝×約190㎝となりかなり小さくなります。
厳密にいうとここまで小さくなることはなかなかありませんし、幅と丈が均等に縮むこともありませんが、カバーのサイズもあわなくなりますし、純粋にお布団が小さくなってしまい寒さを感じるようになる恐れがあるので注意が必要です。
特に綿100%の生地を使用しているお布団の場合だと縮みやすいので注意してください。
お布団に使われる生地の特徴について詳しく知りたい人は布団カバーやお布団の生地の特徴と選び方について【生地が変われば寝心地変わります】という記事で解説しているので参考にしてみてください。

高温で乾燥させることによって羽毛が傷む
これは羽毛布団の場合になるのですが、水洗いしたあとの羽毛は水気を含んで玉のように丸く固まってしまいます。
これが乾燥させるとほぐれてふっくらと大きくなっていくのですが、羽毛に必要な油分が失われていきます。
羽毛はタンパク質でできているので高温で乾燥させるとダメージが加わり割れてしまい、元のふくらみや保温性が失われてしまいます。
一度壊れてしまった羽毛は元通りになることはありませんし、結果的に羽毛布団の寿命を縮めてしまうことになります。
タンブラー乾燥がダメならどうすればいいのか


デメリットについては解説しましたが、とはいえ洗った後は乾かさないと使えません。
ここでは4つの解決方法を解説していきます。
クリーニングに出す
そもそも自分で洗うのではなくクリーニング業者に任せる。
お金がかかるという点を除けばこれが一番おすすめです。
正直、お布団って洗うことはかなりの重労働です。
ですので、クリーニング業者にお任せしてしまうというのもひとつの解決策です。
羽毛布団の場合だと夏場は使わないことも多くしばらく預けていても問題ありませんし、中綿までしっかりと洗ってもらえます。
問題の乾燥についてもプロのノウハウがありますので安心です。
万が一、何か不具合が出た場合でもクリーニング業者によりますが保障してもらえるケースもあり、安心感で言えば1番ですね。
おすすめは寝具の専門店のクリーニングサービスを利用するかネットで申し込みができて自宅まで引き取りとお届けしてくれるクリーニングサービスがいいですよ。
街のクリーニング屋だと衣類に関してはプロだとは思うのですが、寝具はノウハウがないところがやると臭いの問題がおこったりすることがあるので、寝具の専門の業者がおすすめです。
実際に僕が羽毛布団をクリーニングに出した感想を羽毛布団を宅配クリーニングのフレスコで洗った感想を写真付きで解説!【評判や口コミも】という記事で解説しています。
実際洗う前と洗ったあとでどう変わったか画像付きで解説していますので参考になるかと思います。
打ち直し(リフォーム)に出す
そもそも自分で洗うのではなく、いっそのこと作り直すというのも解決方法です。
お布団を洗いたいと思う時点で現状のお布団に不満があるはずです。
生地を洗って清潔にしたい、中綿をしっかりと洗って清潔にしたい、中綿のふくらみが無くなってきて寒い思いをしているなど理由は人それぞれあると思います。
打ち直しをしたら中綿をしっかりと洗ってもらえて、なおかつダメージを受けている羽毛を取り除いて新しい羽毛を足してもらうことができます。
生地も新品の側生地に取り換えてもらうので清潔で洗うより確実です。
費用はかかりますが、自分の手間を省くという点と10年以上使ってるような古い羽毛布団でなければ早い段階で一度検討してみて欲しい方法です。
打ち直しについて羽毛布団の打ち直しとは?お得な人と損する人の違いを解説【サイズ変更も可能】という記事で解説していますのでご覧ください。
天日干しする
やっぱりクリーニングに出すのも打ち直しに出すのもお金がかかって難しい。
コインランドリーで洗って安く済ませたい、そんな人には天日干しもありっちゃありです。
ご家庭でできる天日干しですが、費用はかかりませんが注意点があります。
主な注意点は3つです。
- 風通しのいい場所で干す
- 中綿をしっかりと乾燥させる
- 1日で乾かせるとは思わない
1つめの風通しのいい場所で干すというのは特に解説はいらないかと思いますが、ここでの注意点は日差しの強い日は側生地の劣化を防ぐためにもシーツなどをかけて干すようにしてください。
直接干してしまうと生地が色落ちする可能性が高いです。
物干し竿を2本使ってM字型にして干して、2時間に1度程度裏返して干すとより効果的です。
裏返しにするときに、中綿(羽毛も含めて)をぽんぽんと軽くほぐしてあげると偏りにくくなるのでおすすめです。
2つめの中綿をしっかりと乾かすという点ですが、ここが一番重要です。
ここをしっかりとやっておかないと臭いの原因になったり雑菌が繁殖することにもなりますので注意してください。
側生地が乾燥していても中綿までしっかりと乾いているとは限りません。
乾いたかなと思ってからも余分に干すことをおすすめします。
3つめの1日で乾かせるとは思わないというポイントは2つめで解説した中綿を完全に乾かすためにも頭に入れておいてください。
表面の側生地は乾いていても中綿まで乾いていない可能性があるので、ご家庭で天日干しをする時は1日で乾いたと思っても2~3日は天日干しを繰り返すことをおすすめします。
せっかく綺麗に洗ったお布団も中綿が乾いていなくて臭いや雑菌の原因になれば洗った意味がありません。
より確実にするためにも2~3日は手間はかかりますが干すことをおすすめします。
タンブラー乾燥できるお布団を買う
そもそもタンブラー乾燥できるお布団を買ってしまえば問題ありません。
今までは羽毛肌掛け布団やダウンケットなどの薄手の羽毛布団以外は家庭で洗える羽毛布団はありませんでした。
ですが、2020年頃から洗える羽毛布団も出てきました。
クリーニングに出すと羽毛布団はどうしても値段が高くなりがちですが、自分でコインランドリーで持ち込んで洗えば費用は半分以下に抑えることができます。
乾燥させる場合はネットをかけて乾燥させることをおすすめします。
必要ないと書いてあってもかけておいた方が、ひっかかりのリスクも減らすことができますよ。
詳しくは【2024年3月更新】コインランドリーで洗える羽毛布団のおすすめ3選!【クリーニングいらず】という記事で解説しているのであわせてご覧ください。
2024年のおすすめに更新して内容も良くなっているので参考になるかと思います。
最近ではめっちゃ増えてきてますしね。
タンブラー乾燥についてのまとめ


タンブラー乾燥についてコインランドリーでする方法がネットでも見かけることは多いですが、個人的にはおすすめしません。
費用と手間を考えればコストパフォーマンスがいいとは思いますがお布団が使い物にならなくなるリスクもあります。
どうしてもタンブラー乾燥をする場合は自己責任になってしまいますし。
そんなリスクを背負うぐらいならクリーニングに出すのが一番安全でおすすめです。
そもそも布団を持っていくのも手間ですし、乾燥させる時間もかかります。
それだったら業者に任せて時間を有効活用する方がいいですよ。
これは寝具業界の人間の目線でなく個人的にも思います。
お布団を家で洗うと本当に重労働ですし。
たまに洗うお布団ぐらい楽してもいいんじゃないかと思うので、家で洗う前に一度考えてみていただけたら嬉しいです。
ホント家で洗うと後悔する笑
というか後悔したので記事にしました。
ちなみに羽毛布団については【2024年版】羽毛布団で失敗しない選び方まとめ!【おすすめやお手入れ方法も解説】という記事でまとめていますのであわせてご覧ください。
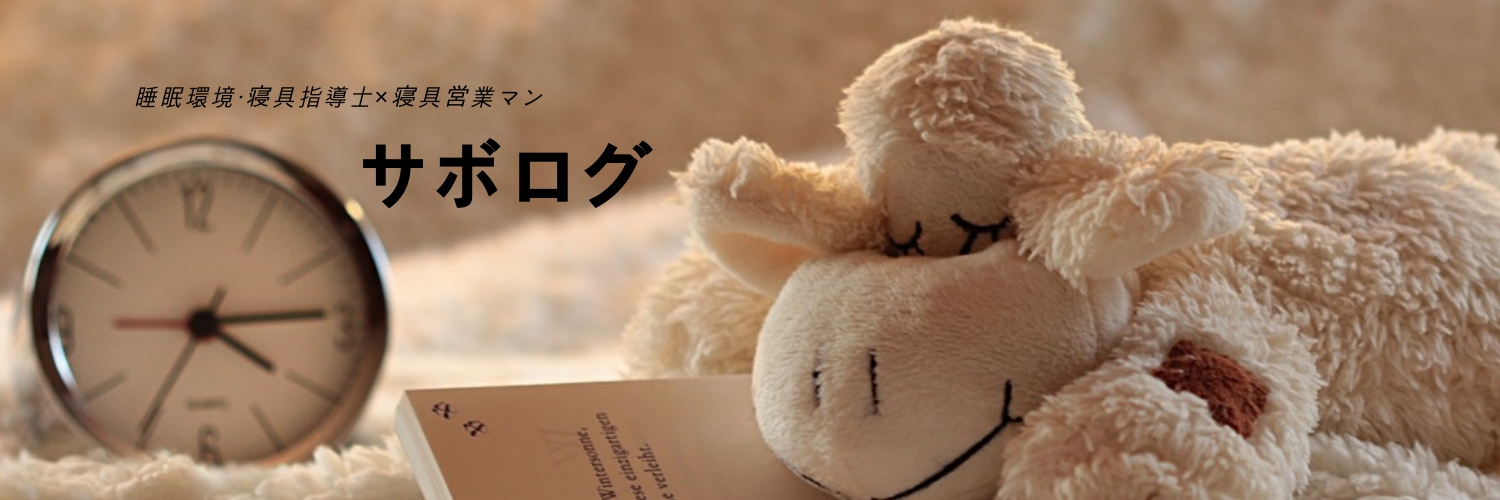

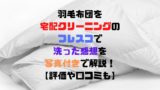





コメント